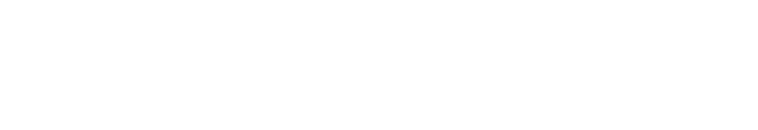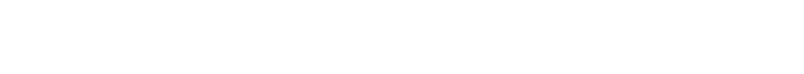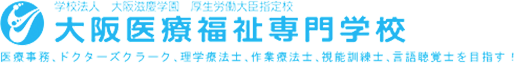知覚の大部分を占める眼の健康を守り、
一人ひとりの“見る”ことにおいての
生活の質を守ることにやりがいを感じます。
視能訓練士学科 3年制
2020年卒業
大阪公立大学医学部附属病院
この職業を知ったきっかけ、目指そうと思った理由を教えてください。
幼い頃に家族が眼の手術のために眼科を受診した際、眼の検査をしてくれる方々の存在を知りました。その頃は幼く、視能訓練士という名前も知りませんでした。その後 中学生になり進路を考え始めた時、母との会話の中で視能訓練士の存在を思い出しました。それまでは漠然と医療の道に進みたいと考えていましたが、そこから視能訓練士について詳しく調べるようになり、大阪医療福祉専門学校のオープンキャンパスに何度も参加しました。『眼鏡が必要な人とそうでない人。同じものを見ているはずなのに、一つに見える人、二つに見える人、色が違って見える人。』など以前は気にしていませんでしたが、よく考えてみると眼には不思議なことがたくさんあります。そこで「眼について専門的に勉強してみたい!」と思い、視能訓練士を目指しました。
現在の仕事内容を教えてください。
勤務時間:8:30〜17:00
仕事内容:眼圧検査、屈折検査、視力検査、眼位検査、視野検査(ゴールドマン視野計、ハンフリー視野計)、眼底検査(造影写真撮影、眼底写真撮影、HRA-OCT、オプトス等)、色覚検査、術前検査などをしています。
職場には視能訓練士が8名在籍しています。ベテランの視能訓練士が複数いるので、自分の検査に責任感は持ちつつも、不安な時は頼れる先輩方に相談できるので、私にとってとても心強い職場です。
仕事で心がけていることを教えてください。
眼科の診療において医師の診察は重要ですが、その医師の診察に必要となるのは視能訓練士による検査結果であると考えています。医師の検査指示の下、時には必要な検査を自らで判断し、信頼性と再現性の高い検査を行うよう心がけています。
仕事の魅力ややりがいを教えてください。
視能訓練士の検査結果によって治療方針が左右されることがあるため、とても専門性が高い仕事です。また、人が受け取る情報の割合はおよそ8割が眼から得ていると言われています。知覚の大部分を占める眼の健康を守り、一人ひとりの“見る”ことにおいての生活の質を守ることにやりがいを感じます。
仕事での心に残るエピソードを教えてください。
患者様の眼鏡合わせをすることがあります。 眼鏡を必要とする患者様に対して、どうすればいかに快適に、そして見やすい眼鏡を処方できるかを考えながら検査をします。
特に記憶に残っている患者様は、既に何本もの眼鏡をお持ちでしたがどれも見えないとのことでした。 眼鏡をどのようなシーンで使うのか(スマホを見たい、パソコンを見たい、テレビを見たいなど)、距離はどれぐらいか等、詳しくお話を聞きました。さらに、一点にのみ焦点が合う眼鏡と複数箇所に焦点が合う眼鏡のそれぞれのメリットとデメリットを噛み砕いて説明し、希望に沿った眼鏡を処方しました。その患者様が再度来院された際、「眼鏡合わせをしてくれた先生ですよね。とても使いやすくて見やすいです!ありがとうございました。」と話をしてくれました。生活の快適さや作業のしやすさに直結する眼鏡が患者様の満足のいくものに出来た時、少しでも生活の中での“見る”ことに対しての質を上げ、感謝していただけて、とてもやりがいを感じました。
大阪医療福祉専門学校の学びや経験は、現在の仕事にどのように役立っていますか?
学内実習に加え、臨床実習や幼稚園健診といった学外実習など実践的な授業が豊富にあるため、実際に臨床に出た時に焦らず行動できました。 また、学年や学科の壁を越えての授業があり、縦と横の繋がりの大切さを学んだことで、現在の職場でも周囲とのコミュニケーションを欠かさず、良い環境を作れていると感じています。
学校生活で印象に残っていることはありますか?
学生ホールや図書室など、授業以外の時間に学習ができる環境が整っており、特に国家試験前によく使用しました。 一人で勉強することもあれば、友人と問題を出し合いながら一緒に勉強したことが印象に残っています。その頃の友人達とは視能訓練士同士として集まったりと、今でも色々なことを相談しあう仲で、心強いです。
将来の夢・抱負をお聞かせ下さい。
病院に来院される患者様一人ひとりの眼の健康に貢献できるよう、検査技術や知識の向上に努めていきたいと思っています。