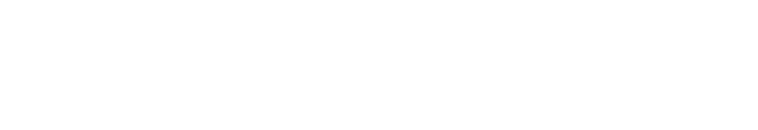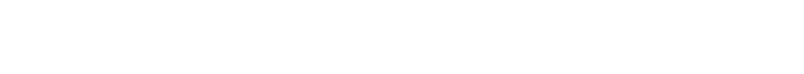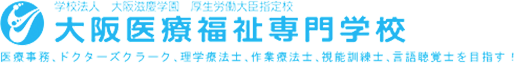診療情報管理士学科「1年生が車いす授業」を行いました!
2013年6月4日
診療情報管理士学科(医療ソーシャルワーカーコース)の教員より、授業をご紹介します。
梅雨の晴れ間ということで、絶好の授業日和となりました 
「晴れだから授業日和・・・?」と思った方、これから詳しくご説明しますね 
医療ソーシャルワーカーコースでは、医療分野はもちろん、福祉分野の授業もあります。
一言で福祉といっても、科目にすると細かく分類されるんです。
例えば、「児童福祉」「社会福祉」「障害者福祉」「高齢者福祉」などなど・・・。
本日は、1年生が「高齢者福祉」について学ぶため、車いすを使って授業を行いました。
中学・高校時に、授業やボランティアで車いすに触れた経験のある学生はいます。
でも、自分が車いすに乗るのは初体験・・・みんな緊張していました。


今回の車いす体験を通して気づいてほしいのは、以下の3点です 
①普段と異なる視線・視界についての気づき
②身のまわりのバリア(障壁)についての気づき
③介護者と被介護者の立場からの気づき
授業を終えた学生さんたちの気づきを見てみましょう 
①普段と異なる視線・視界について
「普段よりも視線が低くなるので、歩行者や自転車がすごく恐く感じた。」
「足元に意識が集中してしまい、視界が狭くなった気がした。」

②身のまわりのバリア(障壁)について
「学校周辺だけでも段差が多い。」
「狭い歩道では、歩行者や自転車がいると通り辛い。」
「歩道にある溝にはまってしまったら、自力では出られない。」
③介助者と被介助者の立場からの気づき
「介助者を信頼することが大切だと感じた。」
「介助者から、些細なことでも声をかけてもらうと安心する。」
「被介助者のことだけでなく、周りのことも気にかける必要がある。」

他にもまだまだたくさんの気づきがありましたよ 
このように、少し視点を変えてみると、普段の社会生活の中でも様々な気づきがあります。
何に気づき、何を変えていくかを考える・・・。
自分の気づきが環境や、人々の暮らしやすさを変えることにつながる職業があります。
興味のある方は、ぜひ一度オープンキャンパスへお越しください