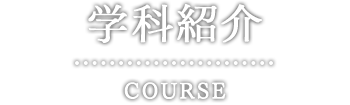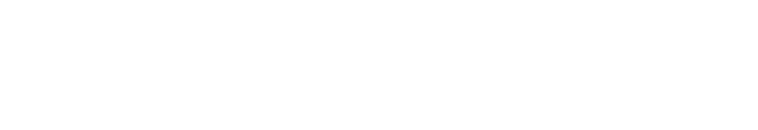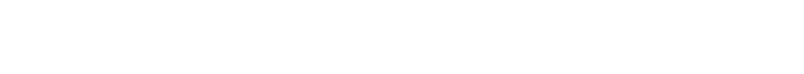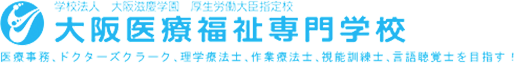言語聴覚士になるには?気になる試験科目から合格率まで

医療や介護の分野で活躍する「話す、聞く、食べる」のプロフェッショナルである言語聴覚士は、国家資格を必要とする専門職です。
基本的に人の生命と財産に関わるような業務は国家資格がなければならないと定められているので、医師や看護師などと同様に、人のコミュニケーションや食事に関わる重要な業務を担う言語聴覚士は資格がなければ職に就くことはできません。
ちなみに国家資格は、医療系以外にも弁護士や会計士、税理士など財産に関わる重要な業務についても国家資格がなければその業務を担うことはできません。つまり、言語聴覚士はこうした重要な国家資格と同様のものであり、有資格者を国が専門家であることを認めています。
言語聴覚士には国家試験がありますが、この国家試験は誰でもすぐに受けられるわけではなく、言語聴覚士の養成課程がある学校を卒業していることが条件になります。

養成課程については、2つのルートがあります。
1つは大学や短大、専門学校などにある言語聴覚士の養成課程に進むルートです。おおむね3年か4年のカリキュラムになっていて、その課程を修了することで国家試験の受験資格が得られます。ただし、卒業見込みの段階で受験が可能なので、このルートから資格試験にチャレンジする人の多くは卒業年次に試験を受けています。
もう1つのルートは、4年制大学を卒業したうえで言語聴覚士の養成課程がある学校に進学するルートです。この場合は大学で一定の過程を修了しているので、その分は再び履修する必要がなく、養成課程も短くなります。
こうした養成課程のある学校、学科に入学するための試験科目は、英語と小論文を基本として、それ以外は国語、社会、数学、理科からの選択制になっているパターンが多くみられます。
なお、大阪医療福祉専門学校の昼間部2年制の一般入試では、国語総合、小論文、面接が試験科目となっています(適性AO入試の場合は学力試験はありません)。いずれにしても小論文試験が含まれている学校が大半なので、このあたりはコミュニケーションを支援する資格である所以ともいえます。この入学試験に合格すると、言語聴覚士の養成課程に入学することができます。
言語聴覚士の養成課程において2年から4年のカリキュラムを修了すると、次はいよいよ国家資格を取得するための国家試験です。
言語聴覚士の国家試験は、毎年2月に行われます。この時期はちょうど、言語聴覚士の学校に通っている方にとっては卒業直前にあたります。そのため、卒業見込みであっても受験が可能です。
試験会場は北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県です。これを見てもお分かりのように、全国の都道府県すべてで行われているわけではなく、人口の多い6都道府県のみです。これらの都道府県以外の方は、最寄りの会場で受験することになります。
試験科目は多岐にわたりますが、言語聴覚士らしい科目が並びます。
試験科目
- 基礎医学
- 臨床医学
- 臨床歯科医学
- 音声、言語、聴覚医学
- 心理学
- 音声、言語学
- 社会福祉、教育
- 言語聴覚障害学総論
- 失語、高次脳機能障害学
- 言語発達障害学
- 発生発語、嚥下障害及び聴覚障害学
すべての科目において、試験は5者択一式の筆記試験です。午前と午後に100問ずつ、合計200問に挑戦します。あくまでも合格の基準は120問以上の正解となっているため、6割を正解できれば合格できる水準となります。
気になる試験の難易度ですが、6割正解できれば合格できるというだけあって、決して簡単な問題ばかりではないといえます。これだけの試験科目があるとはいっても、それぞれの科目でひとつの試験があるわけではありません。上記の多岐にわたる分野から選ばれた200問を解き、合否の判定が行われます。当然ですが、それまでに養成課程で学んできたことをしっかりと理解して身につけていれば、解けない問題はありません。
もうひとつ気になるのが、国家試験の合格率です。
2018年2月の試験実績を見ると、全体の合格率は79.3%でした。おおむね8割の方が合格できているので、何回受験してもなかなか合格しないといった部類の国家試験ではないと思います。
ただ、新卒受験者の合格率が91.3%であるのに対して全体の合格率が79.3%であることです。これを大学受験になぞらえると「現役合格」をしている方が9割を超えているのに対して、「浪人」すると合格率が10%以上も低くなることです。もちろんこの中にはしっかり勉強してこなかった方も含まれていると思いますが、言語聴覚士になるには学校でしっかりと学び、一発で合格することが最も確実であるといえます。
なお、合格した後には、免許証の申請が必要です。医療研修推進財団という団体に免許証の交付を申請し、免許証が交付された時点で「国家試験の合格者」から「言語聴覚士の有資格者」となることができます。
需要が高いと言われる一方で、実際の就職はどうなのでしょうか。
大阪医療福祉専門学校の言語聴覚士学科を卒業する方は大卒者・社会人経験者のため、「自分でも就職ができるのか」「30代からの挑戦でも大丈夫なのか」を気にする方もおられます。
大阪医療福祉専門学校は開校20年以上が経つ伝統校ですが、20代・30代の方はもちろん40代の学生も全員就職し、言語聴覚士として働いています。
このことからも言語聴覚士の需要の高さは伺えますが、もちろん年齢が高くなると若い方に比べて、就職の選択肢が限られるなど難しくなります。学費などの費用面や進学のタイミングなどの課題はあるかもしれませんが、言語聴覚士を目指すなら若いうちから挑戦するのがおすすめと言えるでしょう。